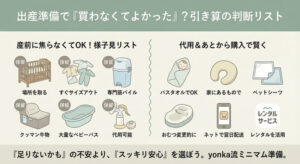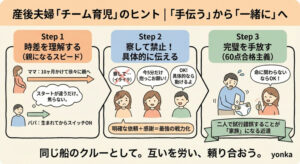ファッションに敏感な方にとって、ヨーロッパブランドの服は特別な存在です。シルエットや生地感、縫製の丁寧さなど、日本国内ではなかなか味わえない魅力が詰まっており、個人で通販サイトから購入する方もいれば、ビジネスとしてヨーロッパから服を仕入れて販売する方も増えています。しかし、その際に無視できないのが「関税」の問題です。関税は商品価格に直接影響するだけでなく、輸入手続きや税金計算にも関わってきます。この記事では、ヨーロッパから服を輸入する際の関税の基本から、個人と商用の違い、関税の節約方法まで幅広く詳しく解説していきます。
ヨーロッパから服を輸入すると関税はかかる?
ヨーロッパから服を日本に輸入する場合、基本的に関税がかかる可能性があります。関税とは、海外から商品を日本に持ち込むときに国が課す税金のことで、その金額は商品カテゴリーや素材、原産地、価格、輸入形態によって異なります。特に「衣類」というカテゴリーは関税の対象になりやすく、課税対象になる確率が高いといえます。
たとえば、フランスやイタリア、ドイツといったファッション大国からブランド服を取り寄せる際、インボイス価格(商品価格+送料)に対して関税率が適用され、さらに消費税も加わります。関税は一般的に約10%前後とされていますが、布地やデザイン、混紡の内容によってはもう少し高くなることもあります。しかも、関税はあくまで「日本の法律」で定められているものであり、現地(ヨーロッパ側)の価格表示や支払い金額とは切り離して考える必要があります。つまり、たとえセールで安く手に入れても、輸入時の課税によって「結局高くついてしまった」というケースも珍しくありません。
さらに、ヨーロッパは関税の原産地規則にも関わってくるため、「どこで作られた服なのか」も重要です。たとえば、ドイツのショップで買ったとしても、その服がバングラデシュで製造されている場合、関税の扱いが異なることもあるのです。ヨーロッパ=関税ゼロとは限らない点には注意が必要です。
個人輸入と商業輸入で異なる関税の扱い
ヨーロッパから服を輸入する場合、「個人輸入」と「商業輸入」では関税の取り扱いが大きく異なります。個人輸入とは、自分や家族で着用するために海外のオンラインショップなどから商品を購入することであり、販売目的ではないことが前提です。一方、商業輸入は明らかに再販を目的としたものであり、事業者としての輸入という扱いになります。
個人輸入の場合は、比較的簡易な通関手続きで済みますが、関税と消費税は免除されるわけではありません。たとえば1万6666円(CIF価格で1万円)を超える場合、関税と消費税が課税されることになります。税関が判断する価格は、実際に支払った金額だけでなく、送料や保険料も含めた総額(CIF価格)です。ここを見誤ると、想定以上の関税がかかることもあるため注意が必要です。
一方で商業輸入になると、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書など複数の書類が必要になり、通関手続きは税関への申告が必須となります。ここでは関税率が明確に商品分類ごとに適用され、輸入者(法人)としての責任も生じます。税率が高くなる場合もあり、また消費税も仕入れ価格に加えて納付する必要があるため、収支管理をしっかりしなければ利益が圧迫される可能性もあります。
関税の税率と計算方法の基本
ヨーロッパから輸入する服の関税は、税関が定める「関税率表」に基づいて課税されます。たとえば、綿やウール、合成繊維などの素材によって細かく分類され、それぞれに異なる関税率が設定されています。たとえば、綿製の婦人服であればおおよそ10.9%、ポリエステルなど合成繊維のシャツであれば8.5%など、具体的な数字が決まっているのです。
さらに、これに消費税(現行10%)が加算される点も押さえておく必要があります。消費税は関税がかかった後の金額に対してかかるため、たとえば関税が2000円だった場合、その金額にも消費税が加算される仕組みです。つまり、合計課税額は想像以上に膨らむことがあります。
たとえば、商品価格が2万円、送料が2000円で、関税率が10%だったとすると、関税額は2200円(2万2000円×10%)になります。さらに、この2万2000円+関税2200円=2万4200円に対して10%の消費税がかかるため、2420円の消費税が加わります。合計すると、輸入時にかかる税金は4620円となります。関税は「見えないコスト」として購入時の判断に大きく関わる要素です。
日EU・EPAを利用して関税を節約する方法
日本とEUの間では、2020年に「日EU・EPA(経済連携協定)」が発効されています。これにより、一定の条件を満たす商品については関税が免除されるという制度が整えられました。衣類もその対象であり、特定の原産地を満たし、適切な証明書が付属している場合は、関税をゼロにすることができます。
ただし、これは誰でも無条件で利用できるわけではありません。「原産地証明書(Statement on Origin)」がインボイスに明記されており、その商品がEUで生産されたことが証明されていなければなりません。また、証明書には特定の文言や輸入者の納税者番号(EORI番号)などの記載が必要となる場合もあり、形式的な要件をクリアする必要があります。
ビジネスとして輸入している場合、こうしたEPAをうまく活用することで、数百枚単位の衣類仕入れにかかる関税コストを大幅に削減できる可能性があります。これは価格競争力の向上にもつながり、最終的には消費者にもメリットをもたらします。一方で、EPA制度を誤用すると通関で止められたり、関税を通常通り課されるだけでなく、追加で審査が入ることもあるため、慎重な書類準備が欠かせません。
到着時の関税支払いとそのタイミング
ヨーロッパから輸入した服が日本に到着すると、多くの場合、税関での検査が行われ、その後配送業者から「関税・消費税の支払い」の通知があります。これが商品到着時に一緒に届けられるケースと、事前にメールやSMSで通知が届くケースとがあります。
支払い方法は、代金引換やクレジットカード、銀行振込など配送業者によって異なりますが、個人輸入の場合は「商品到着時に現金で支払う」ことが一般的です。突然高額な請求が来て戸惑う人も多いため、あらかじめどれくらいの課税がされるのかを調べておくと安心です。
特にEMS(国際郵便)で届く場合は、郵便局の窓口で支払いが必要になることもあり、平日しか受け取れない場合などにはスケジュールにも気を配る必要があります。ビジネスで利用する場合は、税関対応に慣れている通関業者や輸入代行業者を活用するとスムーズです。
まとめ:ヨーロッパの服を賢く輸入するには関税の知識がカギ
ヨーロッパから服を輸入する際、関税に関する知識は非常に重要です。見落としがちなポイントではありますが、ここを理解しているかどうかで、輸入全体のコストや手間が大きく変わってきます。個人であっても1万円を超える商品は課税される可能性があり、また商業輸入では書類や通関の手続きが複雑になることもあります。
しかし同時に、日EU・EPAといった制度を活用すれば、関税を抑えてお得に輸入することも可能です。重要なのは「何を、どこから、どのように輸入するのか」を明確にし、それに合わせた準備を進めることです。ファッションを楽しむうえでも、輸入ビジネスを始めるうえでも、関税の理解は避けて通れないポイントです。正しい知識を身につけて、ヨーロッパの素敵な服をもっと気軽に楽しんでみてはいかがでしょうか。
海外ベビー・子供服セレクトショップyonka
Yonkaは、産まれてきた赤ちゃんとママのための子供服のセレクトショップです。
世界各地から厳選されたお洋服を取り扱っています。
店主自身も子育て真っ最中で、商品のセレクト時には素材の良さや、自分の子供に安心して着せられるかどうかを重視しています。安心して遊べ、見ているだけで癒されるような商品や、大人可愛いアイテムをセレクトしています。
海外子供服の個人輸入・輸入販売に関するご相談
yonkaでは、海外子供服の輸入販売・ネットショップを始めたい方や、始め方がわからない方へのサポートも行っています。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。